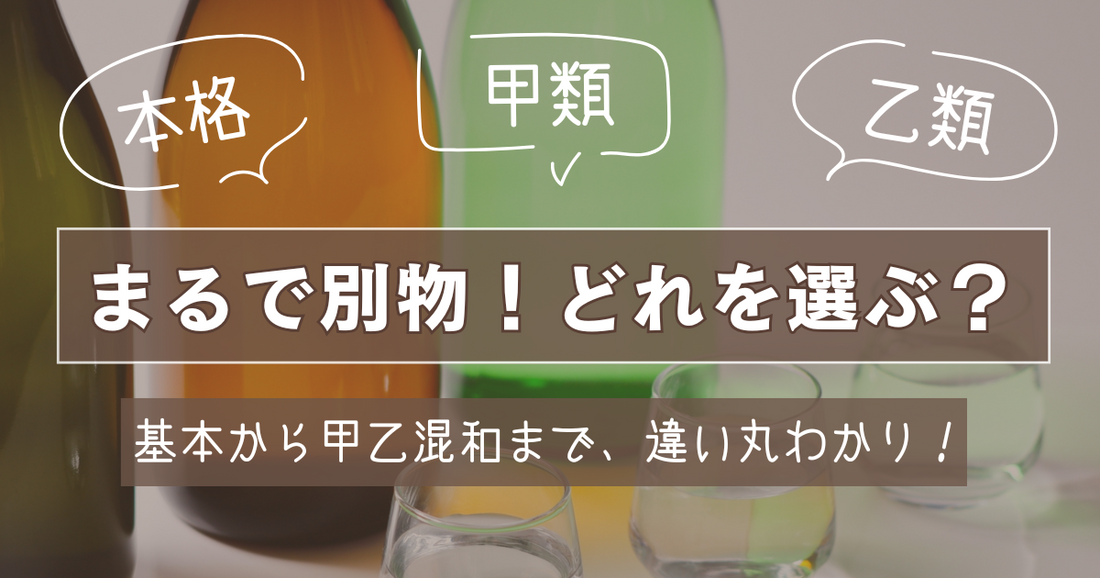
【飲んでるのどっち!?】本格焼酎?焼酎甲類?焼酎乙類?甲乙混和焼酎?それぞれの違い
共有
焼酎甲類と焼酎乙類以外にも種類がたくさん…
焼酎の裏ラベルを見ていると、『焼酎乙類』とか『焼酎甲類』とか『本格焼酎』とか色んな種類があります。ざっと調べると、
- 焼酎甲類
- 焼酎乙類
- 本格焼酎
- 甲乙混和
- 乙甲混和
- 連続式蒸留焼酎
- 単式蒸留焼酎
- 混和焼酎
しかし、
実は大きく3種類しかありません。
まとめると、
| 1. 焼酎甲類 | 連続式蒸留焼酎 | |
| 2. 焼酎乙類 | 単式蒸留焼酎 | 本格焼酎 |
| 3. 混和 | 甲乙混和焼酎 | 乙甲混和焼酎 |
というふうにまとめることができます。
それぞれについて深く説明していきます。
1. 焼酎甲類・連続蒸留焼酎について
特徴(味わいや香り)
無味無臭が最大の特徴です。連続式蒸留焼酎という名の通り、複数回蒸留を行います。これにより、純度が高く、度数の高いアルコールがたくさんとれるようになります。コロナ禍で焼酎メーカーが消毒液を作れたのはこういう背景があります。
製造方法
蒸留を複数回行うことで、アルコールを抽出していきます。
*蒸留とはアルコールと水の沸騰して気体になる温度が異なることを活かして行います。アルコールは80度くらいで気体になるので、お酒を80度で温めていくとアルコールだけを抽出することができます。
原料
サトウキビ、トウモロコシ、米、麦といった穀類や糖蜜類

アルコール度数と用途の違い
販売されるときは、36度未満と定められていますが、市販されているものは20度、25度と一般的な焼酎と同じ度数になっています。
連続して蒸留していくので、最高のアルコール度数は96近くになることは可能です。そこから和水して度数を薄めていくという流れになります。
楽しみ方
「チューハイ」や「サワー」のベースとなっているアルコールがこちらの甲類になります。
*「チューハイ」は、「焼酎ハイボール」の略語です。蒸留酒をベースに炭酸とお好みの味を加えて楽しむのは、バーで飲むカクテルと同じようなものです。
*「チューハイ」と「サワー」の違いについてはこれも後日書きたいと思います!関西は「チューハイ」で、関東は「サワー」という説があります笑
この焼酎がチューハイ等で使われている理由は、芋焼酎や麦焼酎と違って味がないのが特徴です。
代表銘柄
代表的な商品は、
があげられますね。
最近見られる「レモンサワーのもと」といった商品は事前に焼酎甲類とレモン果汁と砂糖などがはいったリキュールに酒税法上分類されています。
2. 焼酎乙類・単式蒸留焼酎・本格焼酎について
特徴(味わいや香り)
芋、麦、米といった素材の風味が残り、しっかりとその素材の味を楽しむことができます。
製造方法
蒸留回数は1回です。
原料
大きく分類すると、芋、麦、米を原料に、「米麹」はどの焼酎にも使用されていることが多いです。芋焼酎に、芋・芋麹の場合や、麦焼酎に、麦・麦麹で使用しているものもあります。
アルコール度数と用途の違い
一般的には20度~25度で販売されています。1回蒸留後のアルコール濃度は38~43となっていますが、和水をして25度に調整しています。なので、原酒と言われるものは、38~43度で販売されています。
楽しみ方の違い
ロックや水割り炭酸割りで芋焼酎や麦焼酎といった焼酎を飲んでいる方はこちらを飲んでいると思います。本格焼酎のことを「乙類」といったり「単式蒸留」といったりします。単式蒸留は酒税絡みでよく見ると思います。
代表銘柄
黒霧島やいいちこといった商品です。焼酎好きは確実にしっている森伊蔵、魔王、村尾もこちらに入ります。フエフーズの本格焼酎は『こちら』
まとめ
| 焼酎甲類 | 焼酎乙類 | |
| 味わい・香り | クセがない | 素材の風味がある |
| 製造方法の違い | 複数回蒸留 | 1回蒸留 |
| 原料 | 穀類(サトウキビ、麦) | 芋、麦、米 |
| 楽しみ方の違い | チューハイ、サワー |
食事とペアリング |
3. 混和【甲乙混和焼酎≠乙甲混和焼酎】という深み
甲乙混和と乙甲混和は、焼酎乙類と焼酎甲類をブレンドした商品になります。名前の違いは、ブレンド比率になります。甲乙混和の場合は、甲類の方が多い場合です。乙甲混和の場合は、乙類の方が多い場合になります。
*豆知識ですが、焼酎乙類と焼酎甲類にはそれぞれ製造免許があり、乙類免許しかもっていないところは乙甲混和しかつくれず、甲類免許を持っていないところは甲乙混和しか作れません。
このブレンド商品の特徴は、『価格』になります。今まで触れていませんでしたが、商品の製造原価は、『焼酎乙類』>>『焼酎甲類』くらいのイメージを持たれるといいです。主な理由は原料代です。味を出すために必要とする麦や米や芋といった原料が異なっているためです。
ブレンドしていることによって製造原価を抑えることができ、販売価格を安くすることができます。
代表的な商品はすごいも、すごむぎ、鍛高譚といった商品です。
こんな感じでなんとなく違いが判っていただけたらと思います!焼酎は価格的に日本酒よりもお手頃であるので皆さんに馴染みがあると思っています。だからこそ違いもわかってそれぞれの良さを知って頂けたらと思います。

